2025年4月26日(土)
ポンポン山の竈ヶ谷に季節の花を求めて歩きました。
ちょうど良い時期だったようで、イチリンソウ、ニリンソウ、ヤマブキソウをはじめ、ヤマシャクヤク、ヤマエンゴサク、ヤマネコノメソウ、ヤマルリソウ、フタバアオイなど、多くの草花を見つけることができました。ネットなどで調べると、竈ヶ谷には他にも私が見つけることができなかった多くの草花があるようです。
大原野森林公園の森の案内所で、竈ヶ谷に入る届を出して出発します。
大原野森林公園はいろいろと経緯があった後、京都市がゴルフ場建設予定地を47億円余りの公金を払って買い取り、市の公園としたものです。ポンポン山の西尾根と東尾根の間の竈ヶ谷を中心にした134haの地域で、これだけ大きな市有地の公園は珍しいのではと思います。
森の案内所を出てから15分ほどで沢を渡り、竈ヶ谷(かまがだに)に入ります。
沢の入口あった、まだ蕾ですがオオバタネツケバナらしい。

最初はスギなどの常緑樹が多いですが、途中からは明るい落葉樹の谷となり、小さな渡渉が何度もあります。

ポンポン山も近年シカの被害が大きいため、多くの草花は鹿よけ柵の中にあります。
一面に広がるのはフタバアオイです。

江戸では「この紋所が目に入らぬか」の、水戸黄門の決め台詞で有名な徳川家の家紋ですが、
京の都では、5月15日に行われる京都三大祭りの一つ、葵祭で冠や衣装、御所車にこのフタバアオイが飾られます。
葵祭には約1万6000本のフタバアオイが必要で、以前は上賀茂神社周辺の山で採れていましたが、近年数が減ってきたため、京都内外の学校や会社、個人で育てて神社に納める「葵プロジェクト」で育てています。

まっすぐ立っているのはヒトリシズカと思いますが、まだ花は咲いていません。

ミヤマカタバミはあちこちに見られましたが、花は終わっていました。

オオキツネノカミソリも鹿よけ柵の中に密生しています。7月から8月にかけて橙色の花を付けます。オオキツネノカミソリもフタバアオイも一般に毒成分があると言われていますが、最近はシカの被害があるということです。

ニリンソウです。一つの花が先に咲き、その後で二つ目が出てきますので、よく見ると二つの花軸の長さが違っています。まだ蕾もあります。

少し先の鹿よけネットの外にあったニリンソウで、二輪あることが良く分かります。

これはイチリンソウです。

少しピンクかかっているようにも見えます。

別々の写真で見るとイチリンソウとニリンソウはあまり区別できませんが、一緒に咲いているところを撮ると、イチリンソウはニリンソウよりはるかに大きく、違いが分かります。また、下のイチリンソウの葉と、上のニリンソウの葉は切れ込み具合が微妙に違います。

少し先の鹿よけ柵の中の斜面が、ヤマブキソウで黄色に染まっています。

ポンポン山は、京都府ではヤマブキソウの唯一の自生地と言われています。シカの食害によって一時はほとんど花が見られなくなりましたが、ボランティアの協力も得て鹿よけネットを設置した結果、本来の生育状態に回復しました。ただし、ネットの中だけでが。

ヤマブキソウと一緒にニリンソウやイチリンソウも咲いています。これはニリンソウですが、ヤマブキソウはニリンソウよりは大きく、イチリンソウと同じくらいの大きさです。

ヤマネコノメソウです。ネコノメソウの仲間は50以上あるようで、果実が裂けるとネコの目のように見えるのでその名が付いたということです。

上の方を拡大するとこんな風にお皿の上に種ができていて、これが猫の目に見えるのでしょうか。雨滴によって種を拡散するためらしいですが、植物もいろんな工夫をするものです。

正面から撮れていないのではっきりしないのですが、タチツボスミレではないかと。

ヤマルリソウです。

ミヤマハコベの群生。

ハコベの種類も多いですが、多分ミヤマハコベで合っていると思います。

ヤマシャクヤクが2輪だけ咲いていました。ヤマブキソウ、ムラサキケマンと一緒です

ムラサキケマン、白いのはミヤマハコベですが、その前にたまたま細かい花弁の白い花が写っています。

拡大するとツルカノコソウかも。もっとしっかりと撮っておくべきでした。

竈ヶ谷を半分少し行くと道は左右に分かれていて、その先は入れません。30年ほど前は、頂上近くの稜線までかすかな踏み跡がありましたが、今は歩けません。
開園時期の終わった福寿草群生保護エリアを通り、西尾根に出ます。新緑の明るい森が広がっています。
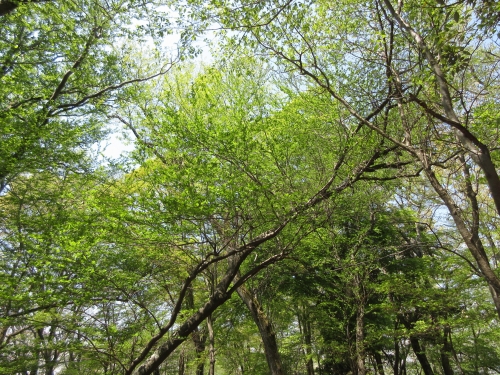
ポンポン山頂上を往復後、西尾根を下ります。途中にあるツツジの丘は、少し時期が過ぎていました。

竈ヶ谷も古くは里山として利用され、今では珍しい草花も当たり前のようにあったのだと思います。こうした里山は宅地開発やゴルフ場開発によって破壊されたものもあり、ポンポン山も危ない所でした。
また、それ以上に近年では、人が薪や炭のために木を切ったりして自然を利用しなくなったために、山が荒れていることが問題になっています。そのままでは暗い常緑樹中心の森(これも一つの自然ではありますが)になってしまいます。
さらに20年ほど前からはシカの食害がひどくなり、シカの好まないアセビが増えるなど、シカが自然の姿を決める時代になってきました。
また、私たち登山者によるオーバーユースの問題もあるかもしれません。
竈ヶ谷は京都市所有の公園でもあり、ボランティアの方の努力もあっていろいろと対策がなされていますが、鹿よけネットなしでも昔のような多様性のある里山に戻るのには、多くのハードルがあります。
それでも来年の春になれば、また同じような草花に出会えるでしょう。こちらが大丈夫かどうかは分かりませんが。
大原野森林公園について、詳しくは以下の資料を見てください。
多様な生きものに恵まれた里山 「大原野森林公園」の魅力
https://ikimono-museum.city.kyoto.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/240223_%E7%B7%91%E3%81%AE%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%EF%BC%88HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8%EF%BC%89%E4%BF%AE%E6%AD%A3.pdf
環境省の「重要里地里山500」選定 大原野森林公園
https://ikimono-museum.city.kyoto.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/7.%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E9%87%8E%E6%A3%AE%E6%9E%97%E5%85%AC%E5%9C%92.pdf
シカの食害から植生を守る 大原野における植生保全の事例
https://ikimono-museum.city.kyoto.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%81%AE%E9%A3%9F%E5%AE%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E6%A4%8D%E7%94%9F%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B_%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E9%87%8E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%A4%8D%E7%94%9F%E4%BF%9D%E5%85%A8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B.pdf
大原野森林公園はいろいろと経緯があった後、京都市がゴルフ場建設予定地を47億円余りの公金を払って買い取り、市の公園としたものです。ポンポン山の西尾根と東尾根の間の竈ヶ谷を中心にした134haの地域で、これだけ大きな市有地の公園は珍しいのではと思います。
森の案内所を出てから15分ほどで沢を渡り、竈ヶ谷(かまがだに)に入ります。
沢の入口あった、まだ蕾ですがオオバタネツケバナらしい。

最初はスギなどの常緑樹が多いですが、途中からは明るい落葉樹の谷となり、小さな渡渉が何度もあります。

ポンポン山も近年シカの被害が大きいため、多くの草花は鹿よけ柵の中にあります。
一面に広がるのはフタバアオイです。

江戸では「この紋所が目に入らぬか」の、水戸黄門の決め台詞で有名な徳川家の家紋ですが、
京の都では、5月15日に行われる京都三大祭りの一つ、葵祭で冠や衣装、御所車にこのフタバアオイが飾られます。
葵祭には約1万6000本のフタバアオイが必要で、以前は上賀茂神社周辺の山で採れていましたが、近年数が減ってきたため、京都内外の学校や会社、個人で育てて神社に納める「葵プロジェクト」で育てています。

まっすぐ立っているのはヒトリシズカと思いますが、まだ花は咲いていません。

ミヤマカタバミはあちこちに見られましたが、花は終わっていました。

オオキツネノカミソリも鹿よけ柵の中に密生しています。7月から8月にかけて橙色の花を付けます。オオキツネノカミソリもフタバアオイも一般に毒成分があると言われていますが、最近はシカの被害があるということです。

ニリンソウです。一つの花が先に咲き、その後で二つ目が出てきますので、よく見ると二つの花軸の長さが違っています。まだ蕾もあります。

少し先の鹿よけネットの外にあったニリンソウで、二輪あることが良く分かります。

これはイチリンソウです。

少しピンクかかっているようにも見えます。

別々の写真で見るとイチリンソウとニリンソウはあまり区別できませんが、一緒に咲いているところを撮ると、イチリンソウはニリンソウよりはるかに大きく、違いが分かります。また、下のイチリンソウの葉と、上のニリンソウの葉は切れ込み具合が微妙に違います。

少し先の鹿よけ柵の中の斜面が、ヤマブキソウで黄色に染まっています。

ポンポン山は、京都府ではヤマブキソウの唯一の自生地と言われています。シカの食害によって一時はほとんど花が見られなくなりましたが、ボランティアの協力も得て鹿よけネットを設置した結果、本来の生育状態に回復しました。ただし、ネットの中だけでが。

ヤマブキソウと一緒にニリンソウやイチリンソウも咲いています。これはニリンソウですが、ヤマブキソウはニリンソウよりは大きく、イチリンソウと同じくらいの大きさです。

ヤマネコノメソウです。ネコノメソウの仲間は50以上あるようで、果実が裂けるとネコの目のように見えるのでその名が付いたということです。

上の方を拡大するとこんな風にお皿の上に種ができていて、これが猫の目に見えるのでしょうか。雨滴によって種を拡散するためらしいですが、植物もいろんな工夫をするものです。

正面から撮れていないのではっきりしないのですが、タチツボスミレではないかと。

ヤマルリソウです。

ミヤマハコベの群生。

ハコベの種類も多いですが、多分ミヤマハコベで合っていると思います。

ヤマシャクヤクが2輪だけ咲いていました。ヤマブキソウ、ムラサキケマンと一緒です

ムラサキケマン、白いのはミヤマハコベですが、その前にたまたま細かい花弁の白い花が写っています。

拡大するとツルカノコソウかも。もっとしっかりと撮っておくべきでした。

竈ヶ谷を半分少し行くと道は左右に分かれていて、その先は入れません。30年ほど前は、頂上近くの稜線までかすかな踏み跡がありましたが、今は歩けません。
開園時期の終わった福寿草群生保護エリアを通り、西尾根に出ます。新緑の明るい森が広がっています。
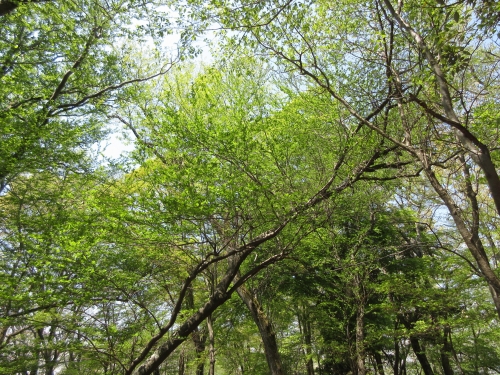
ポンポン山頂上を往復後、西尾根を下ります。途中にあるツツジの丘は、少し時期が過ぎていました。

竈ヶ谷も古くは里山として利用され、今では珍しい草花も当たり前のようにあったのだと思います。こうした里山は宅地開発やゴルフ場開発によって破壊されたものもあり、ポンポン山も危ない所でした。
また、それ以上に近年では、人が薪や炭のために木を切ったりして自然を利用しなくなったために、山が荒れていることが問題になっています。そのままでは暗い常緑樹中心の森(これも一つの自然ではありますが)になってしまいます。
さらに20年ほど前からはシカの食害がひどくなり、シカの好まないアセビが増えるなど、シカが自然の姿を決める時代になってきました。
また、私たち登山者によるオーバーユースの問題もあるかもしれません。
竈ヶ谷は京都市所有の公園でもあり、ボランティアの方の努力もあっていろいろと対策がなされていますが、鹿よけネットなしでも昔のような多様性のある里山に戻るのには、多くのハードルがあります。
それでも来年の春になれば、また同じような草花に出会えるでしょう。こちらが大丈夫かどうかは分かりませんが。
大原野森林公園について、詳しくは以下の資料を見てください。
多様な生きものに恵まれた里山 「大原野森林公園」の魅力
https://ikimono-museum.city.kyoto.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/240223_%E7%B7%91%E3%81%AE%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%EF%BC%88HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8%EF%BC%89%E4%BF%AE%E6%AD%A3.pdf
環境省の「重要里地里山500」選定 大原野森林公園
https://ikimono-museum.city.kyoto.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/7.%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E9%87%8E%E6%A3%AE%E6%9E%97%E5%85%AC%E5%9C%92.pdf
シカの食害から植生を守る 大原野における植生保全の事例
https://ikimono-museum.city.kyoto.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%81%AE%E9%A3%9F%E5%AE%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E6%A4%8D%E7%94%9F%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B_%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E9%87%8E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%A4%8D%E7%94%9F%E4%BF%9D%E5%85%A8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B.pdf
K3号

